|

チェ・ゲバラ(Che Guevara)。本名はエルネスト・ラファエル・ゲバラ・デ・ラ・セルナ(Ernesto Rafael Guevara
de la Serna)。1928年6月14日、アルゼンチン生まれ。1967年10月9日、ボリビアのバジェグランデ近郊のイゲラ村の近くで処刑された。39歳。そんなにも若かったのかと今さらながらに驚かされる。
 「わが夫、チェ・ゲバラ
愛と革命の追憶」。本書は彼の妻であったアレイダ・マルチ(Aleida March)の手になる。貧しい農村に生まれた一人の少女が、さまざまな障害を乗り越え、教育学部の学生となる。米国の後ろ盾を受け、独裁政治を続けていたバティスタ政権に対する学生の抵抗運動に参加する中で、彼女は、都市部の抵抗勢力と山岳部に潜伏していた武装グループの連絡役を務める。 「わが夫、チェ・ゲバラ
愛と革命の追憶」。本書は彼の妻であったアレイダ・マルチ(Aleida March)の手になる。貧しい農村に生まれた一人の少女が、さまざまな障害を乗り越え、教育学部の学生となる。米国の後ろ盾を受け、独裁政治を続けていたバティスタ政権に対する学生の抵抗運動に参加する中で、彼女は、都市部の抵抗勢力と山岳部に潜伏していた武装グループの連絡役を務める。
チェ・ゲバラとの出会い。最初は司令官と部下の関係。やがて彼女はチェ・ゲバラの秘書役を務めるようになる。激しい戦闘を続ける中で、二人は信頼関係を築き、男女として意識し始める。プロポーズは首都ハバナ侵攻の戦闘の最中だった。
革命が成功した後も、彼女は、政権内でのチェ・ゲバラの活動に常に寄り添い、ボリビアへの最後の旅へと彼を送り出す。
チェ・ゲバラへの思い出が多くの逸話と共に、個人史として綴られている。一方で、革命政権内で主要な役割を担ったチェ・ゲバラの最もそばにいたことから、キューバ革命の裏面史としても捉えられる。

2月19日、フィデル・カストロ(Fidel Castro)国家評議会議長は国家評議会議長と軍総司令官を引退すると党機関紙グランマウェブ版で発表。議長職などを実弟のラウル・カストロ(Raul
Castro)に委譲した。ラウル・カストロは、携帯電話の利用規制を緩和や電化製品の一般販売の許可など、新たな施策を次々と発表している。
▼(C)AFP
現在のキューバをどのように捉えるのかは意見が分かれるだろう。一党独裁による専制的な政権であり、政治犯などは劣悪な環境下に収監されているとも聞く。いぜんとして米国の経済制裁が続く中、街中にはポンコツ車が走り、食料事情も改善されていない。
一方で、恒常的な国家財政の逼迫の中で、教育と医療の無償化は継続している。今後、キューバがどのような体制へと向かうのかはキューバ国民が、自らの意思によって決定するべきことだ。
死後30年目を迎えた1997年 、チェ・ゲバラの遺骨は、処刑された同志と共に発掘され、ハバナに移送された。本書には、その追悼式典の際に、チェ・ゲバラの娘が読み上げた謝辞が収録されている。そこには、家族としての親愛の情を超えて、いまださまざまな問題を抱え、苦闘しているラテンアメリカの民衆へ向けられたチェ・ゲバラの思いが秘められていた。
その意味では、エルネスト・ラファエル・ゲバラ・デ・ラ・セルナがチェ・ゲバラとなる前に訪れ、変革への意思を確固たるものとした旅「モーターサイクル・ダイアリーズ」は次の世代へと引き継がれている。
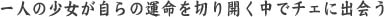
アレイダ・マルチは1936年、キューバ中部の典型的な農村地域であったロス・アスーレスに生まれ、五人兄弟の末っ子として育つ。父のファン・マルチはスペインのカタルーニャ系で都会出身の農民で、読書を好む教養人だった。母のエウドクシア・デ・ラ・トーレは純粋な農民出身で、「鉄のような性格をもち、言動も断固としていて、粘り強い人」だった。少女時代の彼女は、豊かな自然の中で、両親からの愛情を受けて育った。その当時の回想には、やがてチェ・ゲバラという人物に出会い、キューバ現代史に立ち会うようになるとは思いもよらなかったと記されている。
彼女は小学校でマリーナ・ウルキーとという教師に出会う。彼女の薫陶を受け、高等小学校に進むため、州都サンタクララへと向かう。その後、師範学校の過程を終え、1953年、ラス・ビジャス中央大学教育学部に入学した。
州都サンタクララにいたことが彼女の運命を思いがけない方向に誘うことになる。バティスタがクーデターで政権を握ったのは1952年3月10日のことだ。米国の利権を守るのを最優先し、国民を省みないバティスタ政権への疑念が強まる中で、1953年7月26日、サンティアゴ・デ・クーバのモンカダ兵営への襲撃事件が起こる。彼女がフィデル・カストロの名前を聞いたのは、それが最初だった。それでも、まだ、その時期の彼女は映画を楽しみ、友人たちと青春を謳歌するごく普通の女子学生だった。
反バティスタの学生運動に加わる中で、彼女は山岳部の武装グループの連絡役を務めることになり、チェ・ゲバラに出会う。キャンプにいた女性の友人が「どう思う」と聞くと、彼女は「悪くないわ。一番印象的なのは目ね。というより視線ね」と思ったと語っている。
チェ・ゲバラは彼女をどう思っていたのかというと、ある戦闘の最中に、彼女に詩を囁いたという。後に、「自分に関心をもってほしい」との思いだったと彼女は知るが、その当時は、あくまでも司令官と部下という関係として彼女は考えていた。
やがて多くの人が知ることとなり、二人にとって一種のシンボルとなる「スカーフ」事件が起こる。彼女が任務を終え、キャンプに戻ると、チェ・ゲバラが骨にヒビが入った左腕を石膏で固めていた。彼女はスーツケースから黒い絹のスカーフをとりだし、三角巾として彼の腕を吊った。
その後、コンゴ、ボリビアへと転戦する中で、チェ・ゲバラはこのスカーフを片時も話さなかった。敗色も濃くなったコンゴからは「絹のスカーフ....腕を怪我したのではないかと彼女がくれた。愛の三角巾となるだろう」と手紙にしたためている。
やがて彼らは都市部へ侵攻する。目の前に政府軍の軽戦車が見えた。それを撃退する戦闘の中で、チェ・ゲバラは「彼女に何かあったらと思うと恐ろしくなった」と彼女への思いに気づく。

革命成功後、チェ・ゲバラは次々と重要な役職を務めていく。彼女は秘書として彼に寄り添い、二人は結婚する。キューバ危機など乗り越える中で、子供も生まれ、二人はつかの間の平穏の中で、愛を育んでいった。
その頃から、チェ・ゲバラは自らが立ち会ったキューバ革命を理論化する中で、アフリカ、ラテンアメリカなどへの関心を再度、強めていく。そして、それら地域の反体制勢力を支援する活動に乗り出していく。
中継地として選ばれたチェコのプラハに彼が潜伏していた時のことだ。彼は妻が会いに来ることを決して許さなかったが、フィデル・カストロの仲介と説得もあり、彼女は彼の元を訪ねる。周りにはCIAなどの目も光っている。二人での外出には危険が伴う。それでも二人は仲間の目を盗んで、プラハの街を散歩する。そんな、ごく普通の夫婦の情愛も語られている。
心が痛むのは、ボリビアへの最後の旅の直前に、チェ・ゲバラが潜伏していた家を家族で訪ねるシーンだ。国内での潜伏にも関わらず、彼女はホセフィール、彼はラモンと偽名を名乗っていた。しかもチェ・ゲバラは頂頭部を反り、年老いたラモンという人物に変装していた。もの心ついた上の子供を連れて行くと、父親だとわかる。学校ででも話されるといけない。そこで下の娘のセリナと共に彼を訪ねるが、セリナは目の前にいる人物が父親だとは気づかず、「ラモンおじさん」と仲良く、遊んでいた。
チェ・ゲバラの最後の闘いとなったボリビアでの日々。彼が窮地に追い込まれているのをフィデル・カストロは知っていたにも関わらず、彼に救いの手を差し伸べなかったとの伝聞を聞いたことがある。
本書の269ページから270ページにはフィデル・カストロがチェ・ゲバラに送った書簡が掲載されている。
そこには外国への闘いに向かうチェ・ゲバラに対するフィデル・カストロの複雑な心情が吐露されている。最高司令官としては中止せよとはいえない。一方で、個人としては国内に留まって欲しい。少なくとも本書に描かれたフィデル・カストロとチェ・ゲバラの間には深刻な対立は見えない。そして、二人はお互いに尊敬し合い、その友情は最後まで続いていたと語られている。

1997年7月12日、チェ・ゲバラの遺骨がキューバに戻る。追悼の祭典の中で、娘のアレイダが遺族を代表して謝辞を述べた。
「親愛なる司令官。三十年以上も前に私たちの父親は私たちに別れを告げました。統一したボリビアの、そしてマルティの理想を実現するために出立したのです。けれども彼らはまた勝利を目にすることはできませんでした。
父親たちは、この大きな夢は計り知れない犠牲によってのみ実現できると自覚していました。私たちは彼らに再び会うことはありませんでした。
あのころ、私たちはほとんどまだほんの子どもでした。今、大人の男となり、女となりましたが、おそらく初めて、大きな苦しみ、激しい痛みのときを生きています。いかなる事実があったかを知り、そのために苦しんでいます。
今日、私たちのもとへあなた方の遺骨か到着しました。けれども敗北して到着したのではありません。まったく若くて、勇敢で、強くて、大胆な英雄となってやって来たのです。(以下・略)
 チェ・ゲバラの最も優れた資質とは何か。本書では他者、弱者への強いシンパシーだと語られている。映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」で描かれたハンセン病の女性への愛しみ。そんな優しさがチェ・ゲバラを生みだし、彼を果てしなく遠い地平へと連れて行ったに違いない。 チェ・ゲバラの最も優れた資質とは何か。本書では他者、弱者への強いシンパシーだと語られている。映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」で描かれたハンセン病の女性への愛しみ。そんな優しさがチェ・ゲバラを生みだし、彼を果てしなく遠い地平へと連れて行ったに違いない。
誰もが日々の暮らしの中では他者、弱者へのシンパシーを感じながら生きている。しかし、それらは多くの場合、小さな罪悪感と引き換えに、すぐに消えてしまう。時代も状況も違う。誰もがチェ・ゲバラのようには生きられない。ひとつのアイコンとしてのチェ・ゲバラ。彼が主に目指したラインアメリカの諸問題の解決。時に思いだし、考え続けることだけはできる。
映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」と共に上映されたメイキングフィルムの最後には、チェ・ゲバラが国連の議場で行った演説が収められている。何も変わっていないではないかとの無力感と共に、そこで語られている言葉は、何も変わっていないが故に、極めて今日的だ。
「混血のアメリカ大陸の名もない人々。憂鬱で寡黙な人々。彼らは皆、同じ悲しみの歌を歌っている。
しかし今、彼らは自らの歴史を記し始めた。自らの血をインクに、死と苦しみの歴史を記す。今、まさにこの大陸の野原や山で、山のふもとや密林で、街の孤独の中で、川や海の岸辺で、無数の心が動きだした。自らのものを守るため死も恐れずに、500年もの間、奪われてきた権利を取り戻そうとしている。
歴史も、これ以上、この大陸の貧困を無視できまい。搾取と侮辱に耐えてきた人々は今、自らの歴史を自らの手で記し始めたのである。」
戦闘の最中にも愛する女性に詩を囁き、コンゴ滞在時にも、ギリシャ哲学から経済学に至るまで膨大な読書をしていたチェ・ゲバラ。こんな演説を国連で行った政治家はいないのではないだろうか。余りにも文学的で、それが痛ましい。39歳。彼はもう決して老いないし、アメリカの裏庭で、未だに貧困と搾取の中に生きているラテンアメリカの人々に、このメッセージは届いているはずだ。
|
